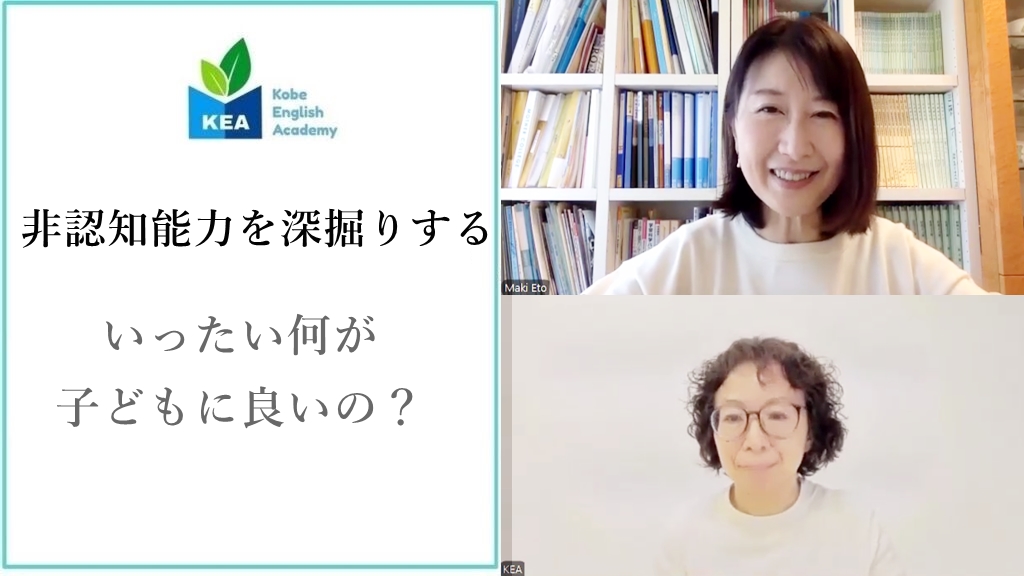コラム記事 #64
非認知能力を深掘りする〜いったい何が子どもに良いの?
神戸イングリッシュアカデミー(KEA)では、皆さんの子育てが少しでも豊かになるよう、「子育てのちょっと困ったこと」について、共に考える機会を設けています。
当ブログでは、保護者様から実際にいただいた質問に、対処のコツや子どもの見方のコツを解説して参ります。毎日の子育てに是非お役立てください!
Ms.Carnell 以下(C)KEA 校長
Ms.Eto 以下(E) KEAプログラムコーディネーター
今日のテーマは、「非認知能力」です。
C)
今日は、過去も取り上げ、たくさん反響をいただきました「非認知能力」について、再び扱いたいと思います。
なかでも多くいただいたのが、
「非認知能力が大切なのはわかるが、具体的にどんな力が大切なのか」
そして
「その力は子どもの将来になぜ必要なのか」
というお声。
今日は改めて非認知能力について考えていきたいと思います。
子どもの非認知能力とは?

E)
非認知能力は幼児期に特に育つということも、かなり広がってきていますので、皆さんの関心が高いこと、よくわかります。ただ、言葉が少し一人歩きしているかもしれませんね。
「非認知能力」という特別な力があり、それを身につけるためにどんなトレーニングが必要なのか、となってしまうと、窮屈な子育てになってしまいます。
なので、まずはいくつかの「非認知能力」をご紹介しながら、それが例えばどんな場面で育まれるのか、その力が将来どのように役立っていくのかについてまとめて見たいと思います。
1. 粘り強さ(GRIT・やり抜く力)
- どんな場面で育まれる?:
パズルやブロック遊びで難しくても諦めずに試行錯誤しているとき
- 将来どんな好影響につながる?:
学校や仕事で困難に直面しても途中で投げ出さず、目標に向かって努力を続ける ことができる
2. 自己制御(Self-control)
- どんな場面で育まれる?:
「おやつはご飯の後」など、欲求をコントロールしなければならない場面
- 将来どんな好影響につながる?:
衝動的な行動を抑え、計画的に勉強や仕事を進められるようになる。社会での信頼 性も高まる
3. 共感力・社会性(Social skills)
- どんな場面で育まれる?:
友達とおもちゃを貸し借りしたり、順番を守ったりする場面
- 将来どんな好影響につながる?:
チームワークを大切にし、人間関係を円滑に築ける。協調性のあるリーダーシップ をとれる
4. 好奇心(Curiosity)
- どんな場面で育まれる?:
「なぜ?」「どうして?」と子どもが関心をもって質問してくる場面
- 将来どんな好影響につながる?:
自ら学び続ける姿勢が身につき、新しい知識やスキルを吸収する意欲が高まる
5. 感情のコントロール(Emotional Regulation)
- どんな場面で育まれる?:
悲しくて泣いている時、「悲しいね」と共感してもらうことで気持ちを切り替える ことができるような場面
- 将来どんな好影響につながる?:
ストレスに強くなり、落ち着いて問題を解決できるようになる
いかがでしょうか。
一気にたくさん紹介してしまいましたが、非認知能力を育てるために何かをするというより、一つひとつの日常生活の場面を工夫しながら過ごすことで、例えば「手出し口出しは少し控えようかな」などができるようになり、そんな中で自然に育っていくのが非認知能力と考えていただければと思います。
非認知能力は、人間としての信頼にもつながる
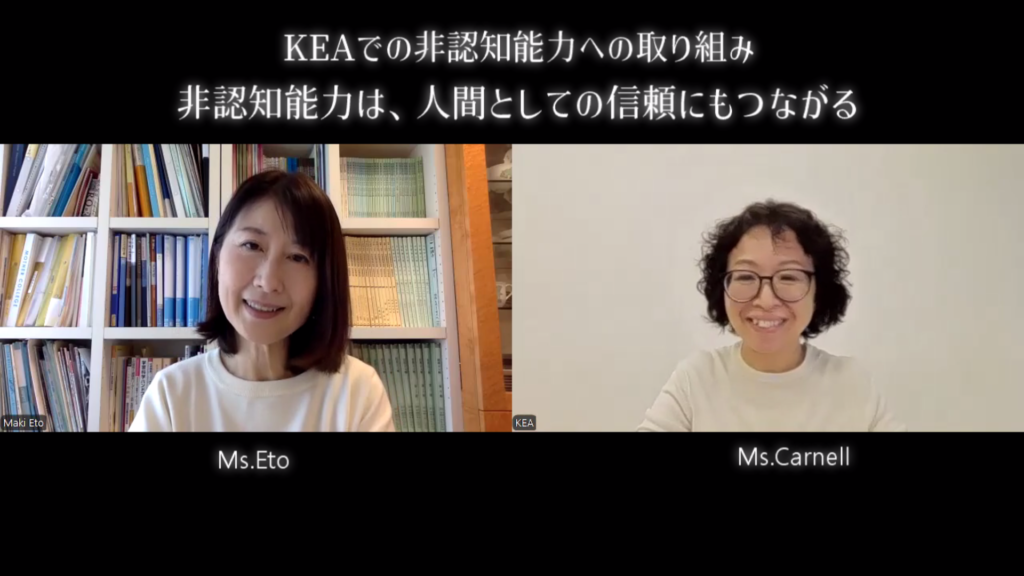
C)
非認知能力にあたるものは、たくさんありますよね。つまり、人間が生きていくための学力以外のもの全てなのかもしれませんね。
私の方で気になっているのは、批判的思考力、クリティカルシンキングです。
今の時代は情報が溢れていて、全てを真に受けるのではなく、自分でこれは正しいのかと立ち止まったり、反対意見を受け入れて議論する力はとても重要と感じます。
アフタースクールのコンピュータークラスでは、子どもたちに画像を見てもらい「これはリアルか」「これは合成されたものか」ということも話題にしていますが、そういう風に見たまま、聞いたままではなく自分で確認し、自分なりに判断する力はこの先ますます重要になっていくと思うんです。

E)
おっしゃる通りですね。批判的思考力というと、何か他者を批判する力のように感じる方もおいでになるかもしれませんが、そうではなく、客観的な視点でものごとを見抜き、論理的に解釈、判断をしていく力のことで、とくに日本人に必要かもしれません。
C)
そして、社会性や感情のコントロール、これも時間がかかることですが、とても重要ですね。
スクールでも子ども同士のいざこざはしょっちゅうあるのですが、なんか子ども同士で解決に向かっている日もあれば、そんな時「めちゃ成長した!」と思うのですが、次の日にまた戻っていたりして、笑。日々「3歩進んで2歩下がる」を繰り返しています。
E)
非認知能力の育成には、とにかく時間がかかるといこと、これは意識しておいた方がいいですね
C)
先日も先生たちが、現場は地味な観察と導きの小さな積み重ねで、昨日と今日では成長がわからないけど、数カ月、1年経ったときに、大きな成長が実感できるんですよね、と話していました。
E)
では、家庭でこういった非認知能力をどう育むことができるのか、3つのポイントをお伝えしたいと思います。
まずは、「見守ること」。どうしても親は心配になって、手出し口出しをしてしまいますが、自分で難しいけどやってみる、そのプロセスこそが大切です。ですから、意識して見守ることを取り入れていただきたいと思います。
そして二つ目は、言語化を意識すること。人間は感情の生き物なので、どうしても感情論になってしまうのですが、子どもにもできるだけ言葉で表現するようにと伝え、そしてご自分もできる限り伝わりやすい言葉で伝えるようにする。そうすることで、スムースに非認知能力が育まれていくと思います。
三つ目は、プロセスフォーカスです。非認知能力は見えない力、すぐに結果、成果とかは「見えない」んですね。それでも子どもを信じて育ちの環境をつくっていくためには、プロセスを見て伝えていくことが大切です。ご自分の焦りも減りますし、子どもが安心できる環境を整えられるようになるはずです。

C)
少し非認知能力に対する理解は深まりましたでしょうか。人が社会で生きていくには信頼関係が重要ですが、信頼というのは、思いやったり、タスクや期待に応える、頑張る姿がキラキラかっこよかったり、そういうものを持っている人が得られるものだと思うんです。
非認知能力は、そんな信頼感にも繋がっていますよね。人に好かれる人は強いというのが私の持論です(笑)。
非認知能力とは、その人の総合力みたいなところもありますので、私たちも引き続き、スクールと家庭との連携を大切に、お子様の非認知能力に意識を傾けていきたいと思います。